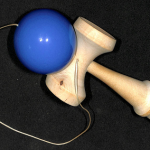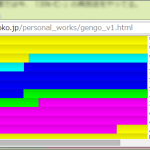読んだ、が…。
 |
![]()
「オートメーション・バカ」のときと同じく、読書録ノート:
Click here to download
オートメーション・バカ、でのそれとは違い、「このノートをみて読みたいと思ってくれれば幸い」というものでもないし、ピックアップした密度も薄いので、このノートだけみても書籍の印象とはかなり食い違うはず。
どこの誰に響くべき本か、どのような人々に好んで読まれる本か。この手の本にはもはや宿命なんじゃないかと思うが、ここに論述されるいかなる主張も、向けられた人々へは響かないことは断言出来るし、響く人々は元々この問題意識は共有しているとみてよい。わかりやすい言葉で言い直そう。「一言一句御意だが、伝わらないだろうなぁ」ということ。
ジャーナリストではないことが幸いし、いや、災いし、この本にはわかりやすい答えなど書かれてはいない。「ありとあらゆる証拠」に基づいて、畳み掛けるように主張するわけでもなく、一つ一つについての証拠能力を、都度都度立ち止まって批評するそのスタイルは、やはり学者のそれだ。しかるに、昭和な PTA のおば様方を喜ばせることがない。答えばかり求める新人類が最も苦手とするタイプの、「思索の実況中継」と呼ぶに相応しいその一貫したトーンにより、決してその意図するところは彼らに伝わることはないだろう。「バカまっしぐら」への加速装置であるところの「○バーまとめ」と対極にあるその学者然とした論考は、そしてますます「ネ○ーまとめ」流儀を遠ざける。
この著述は結局のところ、建設的な主張も楽観的な未来予想もすることなく、淡々と悲観的状況証拠についての論考を積み重ねていくことで成り立っている。しかるにこれは思索のきっかけは与えてくれるけれど、「明るい未来」のための建設的な見方はすべて読者に委ねられていると言ってよい。それはおそらく「「テクノロジー批判」批判」論者たちを喜ばせるだろうが、考える余地を我々に与えてくれる、という意味で有益だ。
けれどもこの「新標準」の世界にあって、新標準に最もそぐわない形でのこうした問題提示が、果たして正解なのかどうなのか。奇しくも書籍の最後に言う「伝統的な印刷物や放送メディアが出発点になるかもしれない」は私には間違いなく真実に思われるけれども、逆説的には、「そうあるべきであること」を主張するのに、もはや「伝統的な印刷物や放送メディアが入り口として適切とは言えない」ことも真だ。
天声人語かよ。
正直読書体験としては、「疲れる」タイプの本。「誰に届くのだ、この有益な主張は」と考えれば考えるほど憂鬱になるのは本当。それと「結論も答えもない」ことが、読者を遠ざけてしまうだろう、というのも本当。
ところでワタシは「CIBER研究所所長デイビッド・ニコラス」の分類で、最古人類に分類されてしまった。「グーグル世代(1994年以降生まれ)」「ジェネレーションY(1973~1993年生まれ)」「ジェネレーションX(1973年より前の生まれ)」と。統計的便宜に過ぎない分類ではあるのはわかってはいるけれど、個人的経験に基づく「世代間断絶」の切れ目とは違っている気がする。
「ジェネレーションX(1973年より前の生まれ)」の境界に位置する私の年齢だと、「低年齢時にコンピュータゲームの家庭への爆発的な普及を経験」した最初の世代に当たる。任天堂のファミコンの登場は小学校中学年、スーパーマリオブラザーズや初代ドラクエなどは、小学校高学年~中学校くらいだ。だから感覚的には私の年齢の前後5年のところにも、大きな断絶を感じる。無論「グーグル世代(1994年以降生まれ)」「デジタル・ネイティブ」にフォーカスするのが当該研究の意図するところであるから、この分類にとやかく言うことでもないのだが。
この本の主張するところを「まとめ」ることは、難しいだけでなくて「それ、やっちゃだめ」なのだけれど、あえて一つだけ選ぶとすれば、「MIND CHANGE の大きさと影響力は気候変動に匹敵する」ということ。
最古人類の烙印を押されてしまったワタシなんぞにとって、この危機感と恐怖感は、身近に差し迫った「リアル」なのだが、あなたにとってはどうだろう?
ワタシのチームに所属していた二人の若者の話。ともに干支で一回り以上違う。「聖徳太子になるな」。一方の若者に向けたかつての言葉。「気が散らないための方法」「集中するという状態」を、どうやら感覚的に身につけていないようなのだ。「答えだけ知ろうとするな」。これを言って泣き出した女の子。どうして答えを教えてくれないんですか、という。信じがたいことだ、と思うも、「答えしか転がっていない」ことに嫌と言うほど馴らされれば、こう育ってしまうのも致しかたがないのかもしれない、と、感情とは別のところで理解しようとは試みる。けれども心底からの理解はやはり苦しいものがある。諦めにそれは近い。